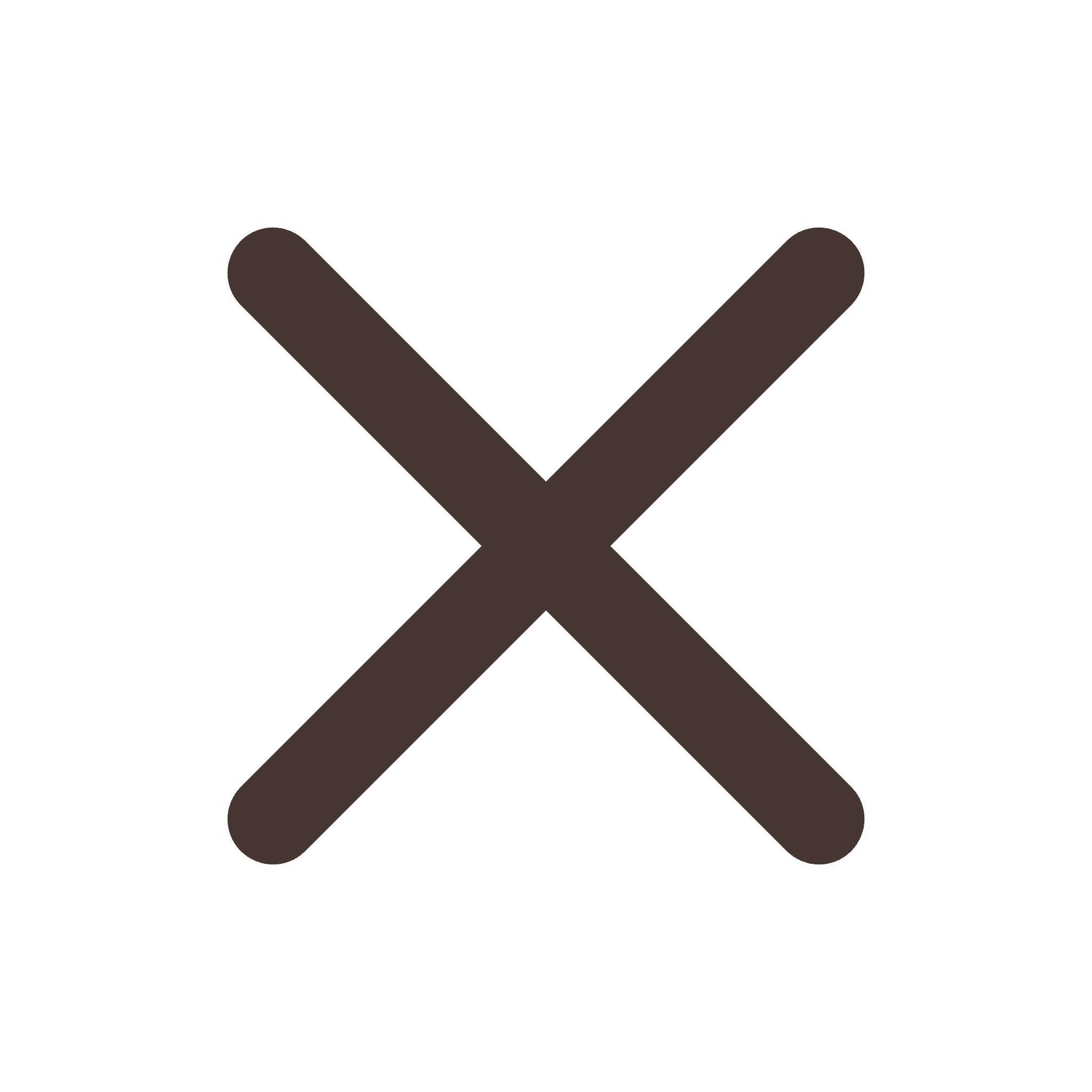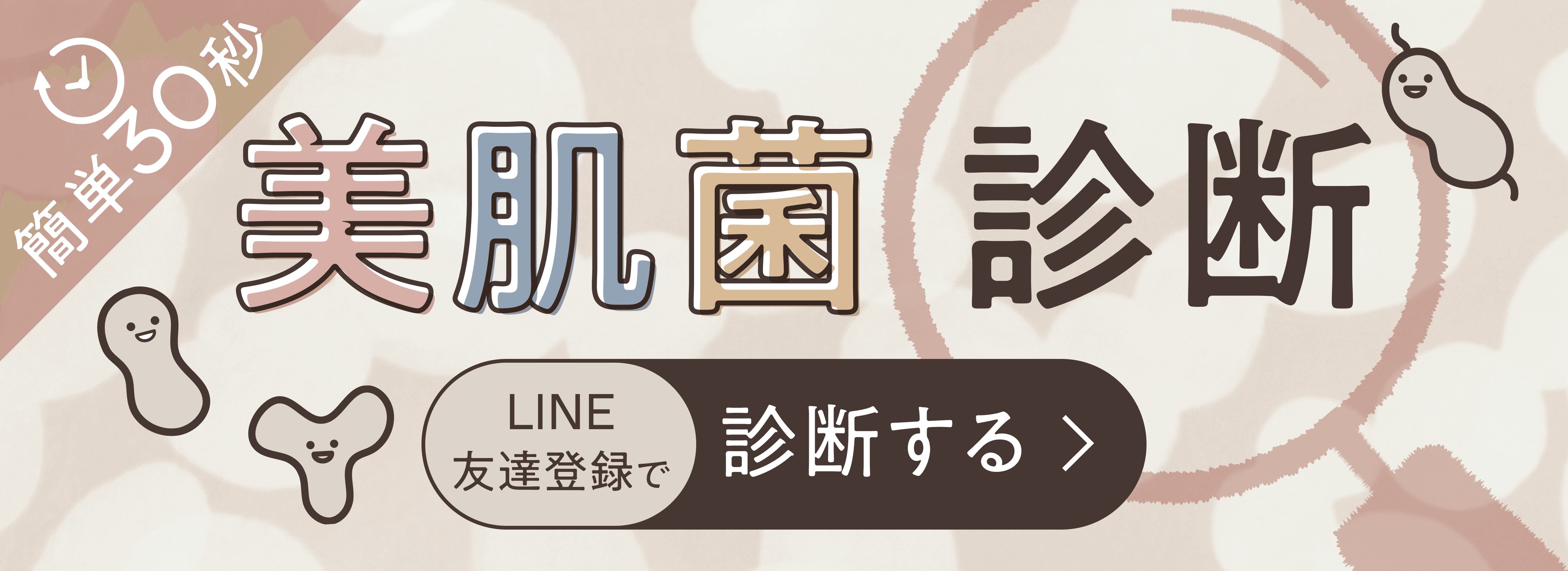菌と歯周病と、口臭と
口から変な匂いがする、友人や家族から口臭を指摘された、などの経験がありませんか?
口臭は歯磨きで磨き残しがある場合や、臭いの強い食べ物を食べた後に発生しやすいとされています。
また、口臭には細菌が関係していることもあります。
そこで、今回は口臭と細菌の関係性について紐解いていきたいと思います。
気になる口臭の原因とは?

口臭の原因と一言で言ってもさまざまです。
そこで、実際に口臭を引き起こすものにはどのようなものがあるか紹介していきます。
また、口臭が起きていなくても、口臭が起きていると錯覚してしまう心理状態もあるので合わせて紹介していきます。
生理的口臭

人間は誰でも少なからず匂いを持っています。
個人の匂いを「口臭」と解釈してしまうことを「生理的口臭」と呼びます。
また、睡眠中は唾液の分泌が減少する関係で、起床したときは比較的口臭が強く出る傾向にあります。これも、生理的口臭の一つです。
ほかにも、空腹時や緊張しているときも唾液の分泌量が減少するため、口臭が強く出やすいです。
このことから、生理的口臭の強弱と唾液の分泌量が関係していることがわかります。
唾液の中には口臭の原因となる細菌を増やさないための「抗菌因子」というのが含まれています。
また口腔内が乾燥すると、細菌の活動性が強くなることから、食事をする・水を飲むなどすれば口臭は劇的に弱くなります。
女性の場合は女性ホルモンのバランスが乱れやすい、月経や妊娠のときに口臭が強く出ることがありますが、これも生理的口臭の一つです。
食べ物や飲み物由来の口臭

ニンニクやネギなどは、独特の匂いを持っており、食後に口臭を発生しやすいです。
さらに、お酒を飲めばアルコール臭を発生させます。タバコを吸っているかたや、コーヒーを嗜好品として楽しんでいる方も同じです。
これらは、生理的口臭と異なり、胃で消化されるなど一定の時間をおかなければ匂いがなくなることはありません。
逆をいえば、先ほど挙げたものを摂取しなければこのタイプの口臭を発生させるリスクがないということです。
病的口臭
鼻や喉に腫瘍ができている、消化器に疾患が発生している、糖尿病や肝臓疾患など全身的な疾患を発症しているなど病的口臭の原因はさまざまです。
しかし、病的口臭と呼ばれる口臭の約90%は口腔内の疾患です。
また、口腔内の疾患を発症させる原因の多くは「プラーク」と呼ばれる細菌です。口腔内に存在するプラークや病気の種類は後述で紹介します。
ストレスによる口臭
ストレスがかかることで、唾液を分泌する唾液腺という組織を支配している自律神経が乱れます。
自律神経の乱れにより唾液が適量分泌されなくなり、細菌が活発になることで口臭が発生します。
生理的口臭と同じような発生メカニズムですが、唾液現象の要因に外界からのストレスがあるため、別個で紹介しています。
心理的口臭
実際に生理的口臭は許容範囲内で匂いを発生させるような飲食物・嗜好品を愛用していないのに関わらず口臭がすると感じることを「心理的口臭」と呼びます。
口腔内にも疾患はなく、健康なのに口臭だけ感じて、歯科医院へ通っていることもあります。
これは、単純に「思い込み」ですが、本人は口臭がすると感じているため、人間が実際に口臭として感じ取る「揮発性物質」が口腔内にどれくらい存在しているかを測定する検査をおこない、数値で納得してもらう必要があります。
検査をしても本人が納得しない場合は、心理検査などを経て心療内科などへ紹介することもあります。
口臭の原因となる病気

病的口臭のところで触れましたが、病的な口臭の90%は口腔内に問題があります。
では、実際にどのような疾患が病的口臭として位置付けられるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
歯周病
口腔内の疾患でも原因として最も多いのが「歯周病」です。
歯周病とは、歯を支える骨や歯茎などの歯周組織が壊れてしまう病気のこと。
歯と歯茎の境目にある「歯周ポケット」と呼ばれる溝の中に細菌が入り込み、増殖することで症状が進行していきます。
主な症状としては、歯磨きをしただけで出血する、歯がグラグラするなどです。
また、歯周病の原因細菌が発生する臭いは腐敗臭のような匂いで、口臭として第三者が感じることになります。
虫歯
虫歯は歯に穴が空いてしまう疾患です。
歯の表面にペリクルという膜が形成され、そこへ虫歯を引き起こす細菌が付着します。
細菌は食べかすや歯磨きの磨き残しをエサに代謝していき、変わりに「酸」を産生します。歯は酸に弱く、長期間酸に晒されることで、穴が開いてしまいます。
一度、虫歯になってしまうと自然には治らず、歯科医院で治療をしなければいけません。
しかし、そのまま放置してしまう方が多く、歯に空いてしまった穴は拡大し続けます。空いてしまった穴の中に食べかすや細菌が入り込んで、腐ってしまうと口臭の原因となる臭いが発生してしまいます。
歯石や歯垢
歯磨きで磨き残しがあるときの口臭は、歯石や歯垢が原因のことが多いです。
これらは細菌の塊であるプラークと唾液の中に含まれるカルシウムイオンが結合して形成されています。
歯石や歯垢が原因の口臭は、これらを除去しなければ匂いを抑えられません。
ガン
口腔内にできる口腔ガンや、消化器にできるガンが原因で口臭を発生することもあります。
しかし、口臭を引き起こす得意的な疾患ではなく、ほかの自覚症状から発覚することが多いです。
口腔内に住む細菌の種類

口腔内には500~700種類に及ぶ細菌が存在しているといわれています。
一般的に汚いというイメージがある便よりも多くの細菌数が存在しているのです。実際にどのような細菌が存在するのか紹介して行きます。
レンサ球菌
口腔内ではレンサ球菌が最も多いです。
レンサ球菌として代表的なのはS.mutansやS.sanguinisなど。
S.mutansとは虫歯の原因細菌の一つで、食事を与える際に母子間で感染する「感染細菌」としても有名です。
歯の全面から検出できる細菌で、虫歯を発生させる大きな特徴を持っています。
歯周病原因細菌
口腔内には歯周病の原因細菌もたくさん存在しています。
例えばP.gingivalisやT.denticolaと呼ばれる細菌です。これらの細菌からは、「内毒素」と呼ばれる毒素が産生されます。
内毒素は歯を支えている歯槽骨を吸収してしまうだけでなく、歯茎に炎症を起こす原因です。さらに、歯周病の原因細菌からは「コラゲナーゼ」と呼ばれる、コラーゲン破壊酵素が分泌されます。
コラーゲンは歯茎や歯と歯槽骨の間に介在している、歯根膜という膜を構成している身体の一部です。コラーゲンが破壊されることで、歯茎がやせ細ってしまい、歯周ポケットがより深くなってしまうのです。
そして、何より歯周病の原因細菌が発生させるものが「硫化水素」や「酪酸」と呼ばれる揮発性短鎖脂肪酸というものです。これらは、口臭の原因となっています。
口腔内の細菌の溜まり場

口腔内でも、細菌はどこに多く存在するのでしょうか。
最も多いのは「歯と歯の間」です。
多くの方は、歯磨きをするときに歯ブラシだけで済ませていることでしょう。しかし、歯ブラシだけでは口の中の約60%しか綺麗にできていません。残りの40%は歯と歯の間に残ったままなのです。
40%の磨き残しもプラークからすれば十分な栄養となってしまいます。そうしてプラークを元に細菌が活発に活動することで、細菌性疾患や口臭が進んでしまうわけです。
口腔ケアで細菌を除去
口腔内の細菌は、ていねいな歯磨きと歯科医院でおこなうクリーニングでのみ取り除けます。
しかし、毎日歯科医院へ通うわけにはいきませんよね。そこで、ていねいな歯磨きをはじめとする口腔ケアを意識してみましょう。
歯と歯の間に残っているプラークはデンタルフロスや糸ようじを使って取り除くと良いです。さらに、奥歯の奥側は通常の歯ブラシでは磨き残しができやすいため、タフトブラシと呼ばれる、先が丸い歯ブラシで清掃すると清潔さを保てます。
また、歯ブラシは手磨きでていねいに磨くことが効果的ですが、場合によっては音波ブラシを使用すると歯石や歯垢が効率よく除去できます。
口腔内の細菌をこまめに取り除いて口臭予防をおこないましょう。
菌ケアで解決?口腔内の対策と効果

さて、口腔内の菌ケアの基本は「ブラッシング」と「治療」です。
歯周病をはじめとした各種疾患がある場合は、まずは治療してしまうこと。日々のケアとしてはやはりブラッシングを行うこと。
私たちは毎日、およそ1.5リットルほどの唾液を飲み込んでいます。そこにはもちろんたくさんの菌が含まれており、腸内環境にも影響を与えます。
とある論文を確認すると、毎日3回以上のブラッシングは腸内に生息するカンジダ菌の数を大きく下げる効果があるとのことでした。
カンジダ菌は腸内の悪玉菌の活性を引き上げる効果がありますので、これを抑えることで腸内環境の改善が見込めます。
先に述べたように、菌のエサになる歯垢や口腔内のネバネバを定期的に落とすことにより口腔内で過剰に雑菌が増殖を抑えることが可能。
そう、日々のケアにおいてはブラッシングがシンプルかつ最重要な菌ケア的取り組みとなります。
注意点として、肌やその他の菌ケアと同様に過剰な殺菌はNG。口腔内にも善玉菌が住んでおり、悪玉菌と戦っています。
例えば、刺激の強いマウスウォッシュは口腔内の菌を無差別に殺菌してしまうので控えた方が菌ケア的にはオススメ。近年、毎日のように使用する方も多くなっているかと思いますので、注意すべきポイントと言えますね。
まずはLINEで友達登録して、気になることをお聞かせください!
あなたに菌ケアのアドバイスをさせていただきますよ。